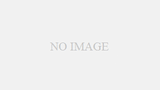DNSの歴史 ― インターネット誕生前からRFCによる標準化まで
インターネットに欠かせない「DNS(Domain Name System)」は、最初から存在していたわけではありません。
その仕組みが生まれるまでには、ネットワークの規模拡大や管理方法の変化など、いくつかの重要な転換点がありました。
1. インターネットの前 ― 名前と住所の管理
インターネットが誕生する前から、コンピュータ同士をつなぐ小規模なネットワークは存在していました。
当時から「コンピュータの名前」と「IPアドレス(住所)」を結びつける必要があり、HOSTS.TXT というテキストファイルが使われていました。
このファイルには、すべてのコンピュータ名とIPアドレスが一覧として記載され、各コンピュータにコピーされていました。
つまり、ネットワーク全体で1つの「静的な住所録」を共有していたわけです。
2. ARPANETの登場と電話帳方式の限界
1970年代、アメリカ国防総省の研究ネットワーク ARPANET が稼働を開始します。
接続するコンピュータが急増すると、HOSTS.TXT の管理に深刻な問題が生じました。
- 新しいコンピュータや変更があるたびに全員へ配布し直す必要がある
- 更新作業に遅れやミスが発生しやすい
- ファイルサイズが増大し、配布や同期が非効率になる
このままではネットワーク規模の拡大に追いつけないことが明らかでした。
3. 分散型管理の発想
1980年代初頭、研究者たちは「名前管理を1か所に集中させる方式」から、「複数のサーバに分散して管理する方式」へ切り替える案を検討し始めます。
この新しい考え方では…
- 名前の情報を階層的に分け、各組織や地域が自分の部分を管理
- 名前を問い合わせる際は、必要なサーバを順にたどって情報を取得
- 更新や追加は担当の管理者が直接行える
これが現在の DNS の原型です。
4. 仕組みの正式化 ― RFCによる標準化
1987年、この新しい名前解決の仕組みは RFC1034 と RFC1035 によって正式に標準化されました。
- RFC1034
DNSの概念や設計方針、階層構造、名前解決の流れなどの基本仕様を定義 - RFC1035
実際のプロトコル仕様やデータ形式、通信手順などの技術的詳細を定義
この2つの文書により、インターネット全体で統一的に動作するDNSの基礎が確立されました。
現在のDNSも、このとき定められた基本設計をほぼそのまま引き継いでいます。
まとめ
- 初期のネットワークでは
HOSTS.TXTによる中央集権型の名前管理が行われていた - ARPANETの拡大で管理・配布の限界が顕在化
- 分散型・階層型の管理方式が考案され、現在のDNSの原型が誕生
- 1987年、RFC1034とRFC1035で正式に標準化され、現在まで続く基盤となった